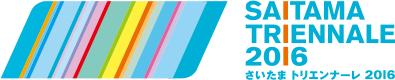ブログ
ディレクターズノート008
花と緑の散歩道を行く
武蔵浦和という駅は埼京線と武蔵野線が交差して、こんなにも東京に近いところに駅があるわけだから、駅前はまさに再開発の真っ只中だ。しかし埼京線に沿うように別所沼公園の方に歩いて行くと、落ち着いた古くからの住宅地が広がっている。今回のトリエンナーレではさいたま市を「生活都市」と捉えたから、私はどうしても住宅地のなかでの展示を考えたかった。そこで新旧住宅が広がった武蔵浦和駅から中浦和駅にかけてのこのエリアを、メインエリアの一つに選んでみた。
具体的には、武蔵浦和の駅を降りると埼京線の高架沿いに「花と緑の散歩道」という散策路が別所沼公園まで続いているので、この道を利用して、散策としてのアート体験を試みている。
道そのものを「アート化」するのはスイス出身のダニエル・グェティン。トリエンナーレカラーをベースに、2色のカラフルなフィルムのラッピングや塗装で、鮮やかかつ印象的なランドマークを作り出してくれた。「ステーション」と呼ばれるパーゴラのような構造物を「花と緑の散歩道」の4箇所に設置したが、ひとつにたどり着くと次のステーションが自然と目に入ってくるから、人は迷うことなく道を進んでいく。
ダニエルのステーションとともに人を誘っていくのが、ウィスット・ポンニミットの《時間の道》という作品。タムくんの愛称で知られるタイの漫画家だが、ここでは道のあちこちに立てられた既存の標識や注意看板に並べて、彼の「ひとことシリーズ」を展開している。メインキャラクターのマムアンたちの愛らしい仕草に的確なひとことがつけられて、しかしこの言葉、本当に深い。それを読みながらブラブラと道を歩いていく。
大胆な色彩で空間にメリハリをつけるダニエル・グェティン、悪戯めいて微笑みを誘うウィスット・ポンニミット。二人の力で、実に魅力的なアプローチが生まれたと思う。そして彼らの作品に誘われて道を進んでいけば、涅槃のポーズで横になった巨大なサラリーマン、アイガルス・ビクシェの《さいたまビジネスマン》が姿を現わす。
正確なデータではないけれど、さいたまからは毎日50万人もの人々が東京との間を行き来していると聞いた。ラトビア出身のアイガルスにとって、いや、誰にとってもだが、信じられない数字であり、一つの都市の人口にも匹敵する。朝の埼京線のラッシュは全国的にも有名だ。そんな過酷なサラリーマンの姿に想いを馳せて、たまには何もかも忘れて横になってほしいと、彼はこの作品を構想した。涅槃像のポーズを参照したから、ここから感じる印象は様々だろう。暖かなユーモアを感じるか、達観した姿を感じるか、あるいは深い哀しみを感じるか?今朝も満員の埼京線が走り去るすぐ横で、アイガルスのサラリーマンは横になっている。
《さいたまビジネスマン》を過ぎたところで「花と緑の散歩道」を離れ、住宅街に入っていくと、旧部長公舎の4棟の建物が現れる。県に出向した部長職用の官舎で、1970年に建てられた鉄筋コンクリート二階建ての住宅。間取りは4棟とも同じである。そこでは4組のアーティストが、それぞれ個性的なやり方で自分たちのプロジェクトを展開している。さいたまトリエンナーレの特徴を端的に示す展示エリアといっていい。どの家でも玄関を入り、靴を脱ぎ、家に上がっていくわけだから、知らない誰かのお宅にお邪魔するような、どこか不思議な戸惑いを感じるはずだ。
野口里佳《はじめのことば》。野口は非常に印象的な芝川の一瞬を、さいたまトリエンナーレ2016のフライヤー、ポスターのために撮り下ろしてくれた写真家だが、さいたまは彼女にとって生まれ故郷でもある。日本を離れ、国際的に活躍してきた彼女が、今、生まれ育った土地に戻って何を感じるのか?何気ない日常の風景の中に、実は「世界の中心」があるのだとあらためて発見していく彼女の心の変化には深く感動する。ホワイトキューブに改装した室内の1階では、野口が写真家として初めて出発した頃の初々しい写真群が、2階ではその時被写体に選んだ消防署で、今回新たに制作したムービーが発表されている。消防訓練を撮った2階のムービーは、まるでバスター・キートンの無声映画を観るようで、こんな世界が我々の日常のすぐ横に存在しているのかと思うと、おかしさがこみ上げてくる。
隣の家に行こう。ここでは松田正隆+遠藤幹大+三上亮が《家と出来事 1971-2006の会話》を展開している。初め、演出家である松田正隆は、この家で架空の家族の物語を役者たちに演じ続けてもらうという構想を持ったようだが、毎日の上演はむずかしいということで、素晴らしい飛躍が生まれた。つまり不在の演劇といったらいいか、空間と深く結びついて聞こえてくる様々な会話や物音、時々点くテレビや電灯や家電、そういった環境の変化だけで、つまり演者は不在のまま、実に生き生きとした室内劇が演じられていくのである。ここにあるのは気配だけだ。本当に魅力的な空間が生まれたと思う。
坂を下り、旧部長公舎7号棟に向かう。ここは鈴木桃子、《アンタイトルド・ドローイング・プロジェクト》の家だ。まず真っ白な部屋が作られ、彼女は白い壁に鉛筆でドローイングを描き始める。その行為は会期中ずっと続けられ、日々、部屋は姿を変え、緻密なドローイングで満たされていく。そして11月20日、私とのトークを合図として、プロジェクトはもう一つのフェーズに入っていく。観客が消しゴムで、ドローイングを消し始めるのだ。そして会期終了日、作家自らがメインのドローイングを消してプロジェクトは終了する。無から生まれ、形を変え続け、また無に戻る。無とは何もないということではなく、純粋な可能性だ。鈴木桃子はこの小さな白い部屋の中で、様々なものが相互に作用し、生成を続ける生命的な宇宙そのものを出現させている。ロンドンや香港で注目されながら、日本では発表の機会に恵まれてこなかったから、彼女にこうした発表の場を提供できたことがとても嬉しい。
そして隣の8号棟。ここは髙田安規子+政子の家。《土地の記憶を辿って》だ。彼女たちはこれまで、見慣れたものや風景を対象に、時間や大きさを異和化する作品を発表してきたが、ここでは間取りには一切手を加えず、2006年以降使われなくなったこの部長公舎そのものの修復を試みている。この場所は縄文期、海が目の前に広がっていて、彼女たちはそのことにも強く刺激されたようだ。貝塚や海岸線を扱った作品もある。見沼田んぼや斜面林に生息する絶滅危惧種の生物をモチーフにした、2階の繊細な切り絵は圧巻。こうした細やかな作品たちが、障子やガラス戸を何気なく彩る。1階にはカフェやショップの機能ももたせ、作品を見ながら畳の部屋でくつろげるようにもしてある。
今回は様々な理由から、トリエンナーレ全体でカフェ機能はここだけにしか設けられず、それがなんとしても残念でならない。とはいえ、このカフェのコーヒーは実にうまい。
部長公舎を後にして、再び花と緑の散歩道に戻る。そして別所沼公園に向かっていけば、公園に渡る歩道橋の上から、池に浮かんだ二艘の「種は船」が鮮やかに姿を現わす。日比野克彦《種は船プロジェクトinさいたま》。日比野はこれまで日本各地で地域や人をつないできた「種は船」2艘を、市民とともにトリエンナーレカラーで彩色し、さいたまバージョンにつくりかえた。その姿は別所沼公園に深く馴染んで、見事なほどだ。しかしそれ以上に驚くのは、彼の感染力と言ったらいいか、さいたまトリエンナーレサポーターを中心に、すでに「明後日新聞社さいたま支局」ができてしまったことだ。こうしてさいたまの人々の心の中に、「種は船」は根付いていく。